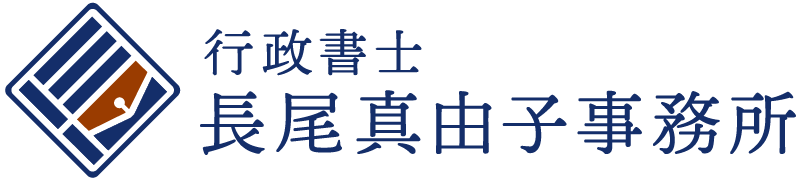はじめに
特定技能1号の外国人労働者を自社で直接支援する場合、登録支援機関に委託する方法と比べて、所属機関として対応すべき事項がより多く定められています。
今回のブログ記事では、自社支援を開始するにあたって、特に問題となりやすいポイントについて詳しく解説していきます。
登録支援機関に委託せず、自社で支援を行う場合に注意すべき主な事項は、以下の2点です。
- 特定技能1号制度で定められた要件に適合する「支援責任者」および「支援担当者」を選任すること
- 外国人が十分に理解できる言語で支援を提供できる体制を整えること
これらの対応は、登録支援機関に委託している場合には同機関が担ってくれますが、自社支援を選択した場合は、すべて自社で実施する必要があります。
この2点を見て、「支援責任者や支援担当者は社内の誰でもよいのか?」「通訳者を常時雇用しなければならないのか?」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、そうした疑問や不安を解消するために、制度上の要件や実務上の注意点をわかりやすくご紹介します。自社支援を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
支援責任者・支援担当者の選任
支援責任者、支援担当者は自社の職員の中から選任します。支援責任者・支援担当者は同一の人物でもかまいません。ただし、自社の職員であれば誰がなっても良いというわけではありません。
過去2年間の経験・実績
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」には、支援責任者・支援担当者について、次のように書かれています。
○ 特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。
① 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること
② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの
(注)法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいいます。
つまり、自社で特定技能1号の外国人支援を行う場合、次のような考え方になります。
所属機関に、過去2年間に就労を伴う中長期在留外国人を適切に管理した実績がある場合は、社内の役員または職員を支援責任者に選任することができます。
一方で、所属機関にそのような管理実績がない場合でも、転職してきた職員などに、過去2年間に就労を伴う中長期在留外国人の生活相談業務の経験がある者がいれば、その職員を支援責任者として選任することで、自社支援が可能になります。
この要件で特に注意すべきなのは、対象となる外国人の在留資格です。支援や相談の対象となった外国人は、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行っていた者である必要があります。さらに、「法別表第1の1の表、2の表および5の表の上欄」に記載された在留資格をもって日本に滞在していたことが条件となります。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動
過去2年間の経験・実績が問われていますが、2年間の間に1回でも経験があれば良く、2年間継続した経験は必要はありません。
支援責任者・支援担当者の配置
支援責任者・支援担当者は同一人物でも構いませんが、外国人を雇用する事業所が複数ある場合は、一つの事業所ごとに一人の支援担当者を配置する必要があります。
支援責任者・支援担当者の立場
特定技能1号外国人の直属の上司は、支援責任者・支援担当者になることができません。特定技能1号外国人に、何か悩みや相談をしたいことがあった時に、中立的な立場の人に相談できるように配慮されているからです。
このことは、「特定技能基準省令第2条」に次のように書かれています。
【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。
四 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。
「外国人を監督する立場にない者」とは、支援対象の特定技能1号外国人に対して、業務の指示や命令を出す権限がない人のことです。
たとえば、外国人と異なる部署に所属していて、直接の指揮命令関係がない職員などが該当します。
ただし、部署が異なっていても、実質的にその外国人に指示を出せる立場にある人は含まれません。
たとえば、代表取締役や、外国人が所属する部署を統括する部長(製造課なら製造部長など)は、形式上部署が違っていても、組織図上で上位にあたるため「監督する立場」とみなされ、支援担当者としては適格ではありません。
外国人が理解できる言語での対応
こちらも、実務では大きな問題となります。結論から言うと、外国人が分かる言語の通訳者が必要になるのですが、社内に通訳者を常時雇用しておく必要はありません。
外国人が理解できる言語とは
特定技能1号外国人の支援を行う際の言語について、以下の規定が設けられています。
【関係規定】
特定技能基準省令第2条
2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の
適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。
二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。
また、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」には、言語について以下のように記載されています。
(2)十分に理解できる言語による支援体制に関するもの
「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。
つまり、必ずしも母国語の通訳を雇用する必要はないということです。日本語能力の高い外国人であれば、日本語でもかまいませんし、英語能力の高い外国人であれば、英語での対応も可能です。
適切な相談体制とは
「特定技能基準省令第2条」には、「当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること」とありますが、このことについて、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」には、以下のように記載されています。
(2)十分に理解できる言語による支援体制に関するもの
「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。
つまり、上記でも記載した通り、常勤の通訳者を社内に抱える必要はないということです。必要な時のみ、社外の通訳者に通訳をお願いすることができます。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
特定技能1号外国人を自社で支援しようとする場合、当然のことながら、今まで登録支援機関に委託していたことも自社で行う必要があり、その為の体制も用意していかなければなりません。
今回のブログ記事では、その体制づくりの際に問題となりやすい、2つのポイントについて詳しく解説してきました。
自社で支援体制づくりをする際の2つのポイント
- 特定技能1号制度で定められた要件に適合する「支援責任者」および「支援担当者」を選任すること
- 外国人が十分に理解できる言語で支援を提供できる体制を整えること
もし、登録支援機関の委託から自社支援に変更したいが、「何から始めて良いかわからない」「制度が複雑で、失敗しそうだ」というようなお悩みがございましたら、一度行政書士長尾真由子事務所にご相談ください。
登録支援機関での就労経験のある女性行政書士が、親身になって応対させていただきます。
参照:特定技能外国人受入れに関する運用要領
第5章 特定技能所属機関に関する基準等
第2節 特定技能雇用契約の相手方の基準
第2 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。