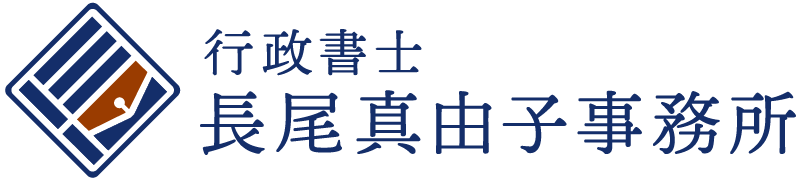2019年に特定技能制度が開始されてから、早や6年が経ちました。現在特定技能の在留資格で日本に在留する外国人の数はおよそ28万人(2024年12月統計)に達しています。
また、2028年には、特定技能全分野で、82万人の外国人の在留が見込まれています。
これだけの外国人を特定技能で受け入れているのですから、そろそろ自社支援に切り替えたいと考えている所属機関(受入れ機関)も多い事でしょう。登録支援機関が入っていることで助かる面もありますが、やはり、登録支援機関に支払う支援費(月額1人につき1万~3万)の負担が重いというお話もよく耳にします。
特定技能1号外国人を自社で支援するきっかけは、コスト削減である場合もありますが、それ以外にも多くのメリットが存在します。
自社支援に関するメリット・デメリットについては、前回のブログ記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
自社支援への切り替えを検討する際に、どのような覚悟や準備が求められるのかが、より明確になるはずです。

この記事では、導入前から運用開始後までの「自社支援スケジュール」を時系列で整理し、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
1. 導入前の準備(1〜2か月前)
外国人材の受け入れが決まったら、まずは社内体制の整備から始めましょう。
|支援責任者・担当者の選任
支援責任者の選任
■ 支援責任者とは
支援責任者は、受入れ機関(または登録支援機関)の役員または職員で、支援担当者を統括・管理する立場の人です。
常勤である必要はなく、非常勤の役員や非正規職員でも選任可能です。
■ 主な職務
支援責任者は、以下の支援業務全体を管理します。
- 特定技能1号の支援計画の作成
- 支援担当者や支援業務従事者の管理
- 支援の進捗確認
- 支援状況の届出
- 帳簿の作成・保管
- 行政機関との連絡調整
- その他、支援に必要な事項の統括
なお、支援責任者自身が面談や同行などの支援を直接行うことも可能です。
■ 支援責任者の選任要件
受入れ機関が支援責任者を選任するには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 受入れ機関として
過去2年間に就労系ビザの外国人を受入れ・管理した実績があり、その機関の役職員(役員でも職員でも可)から選任すること。 - 役職員として
過去2年間に就労系ビザの外国人の生活相談業務に従事した経験がある役職員を選任すること。 - 上記と同程度の能力があると入管庁長官が認めた役職員を選任すること。
要するに、
- 機関として実績がある場合 → 役職員なら誰でも選任可能
- 機関に実績がない場合 → 生活相談経験のある人を役職員として雇用すれば選任可能
という整理になります。
■ 中立性の確保
支援責任者は、支援対象の外国人に対して指揮命令権を持たない立場である必要があります。
そのため、同じ会社内でも、対象者を直接指揮する部署の人は選任不可です。
支援担当者の選任
■ 支援担当者とは
支援担当者は、受入れ機関の役員または職員で、
特定技能1号の支援計画書に記載された支援を実際に実施する人です。
支援責任者と異なり、支援担当者は外国人への支援を日常的に行うため、常勤であることが望まれます。
■ 主な職務
支援担当者は、支援計画書に基づき、次の10項目の支援を実施します。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ側の都合で離職する場合)
- 定期面談・行政機関への通報
■ 支援担当者の選任要件
受入れ機関が支援担当者を選任するには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 受入れ機関としての実績
過去2年間に就労系ビザの外国人を受入れ・管理した実績があり、
その役職員から事業所ごとに1名以上選任する。 - 役職員としての経験
過去2年間に就労系ビザの外国人の生活相談業務に従事した経験がある役職員を、
事業所ごとに1名以上選任する。 - 上記と同程度の能力があると入管庁長官が認めた役職員を、
事業所ごとに1名以上選任する。
ポイントは、
支援を行う事業所ごとに最低1名の支援担当者が必要
という点です。
1名いれば、複数の特定技能外国人を担当することも可能です。
■ 中立性の確保
支援担当者も支援責任者と同様、
支援対象の外国人に対して指揮命令権を持つ立場の者は選任不可です。
支援責任者と支援担当者の兼務
中小企業や個人事業などで人員確保が難しい場合、支援責任者が支援担当者を兼任することは可能です。
これは受入れ機関・登録支援機関どちらでも、事業規模に関係なく認められています。
ただし、
- 支援責任者・支援担当者それぞれの要件を満たしていること
- 支援担当者として業務を行う事業所に所属していること
この2点は必須です。
|翻訳者・通訳者の準備
入管に提出する書類の作成や、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、面談などは、外国人本人が理解できる言語で行う必要があります。
特定技能1号の外国人は、来日当初は日本語能力がN4レベルであることが多いため、社内に翻訳や通訳ができる社員がいない場合は、外部の翻訳者や通訳者と連携することを検討してください。
常駐の通訳者を社内に配置する必要はなく、特定技能運用要領にも書かれている通り、必要に応じてスポット的に通訳・翻訳業務を外部委託することで対応することも可能です。
第5章第2節第2(2)
「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。
抜粋:法務省|特定技能運用要領
|支援計画書の作成
入管庁が求める支援項目(生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談対応など)を網羅した計画書を作成し、社内で共有します。支援計画書は特定技能1号外国人が十分に理解できる言語で書く必要があるため、英語を含む10か国語の支援計画書が、入管のホームページからダウンロードできるようになっています。
参考:特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁
それぞれの言語にいくつかの書類が含まれていますが、「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」が、上記の支援計画書にあたります。10か国語の支援計画書を入手することはできますが、書き込んだ内容については翻訳が必要となることに注意してください。
|記録様式・マニュアルの整備
支援内容は記録・保存が義務付けられています。また、それ以外の書類(入管に提出した書類など)もデータで保存・共有しておくことをお勧めします。どのような書類をいつ、どこに提出したかを保存しておくことで、入管からの問い合わせや追加資料の請求、次の在留資格更新書類の作成時にスムーズに対応することができます。各種書類の保存先としてクラウドサービスを、コミュニケーションツールとしてSlackやChatwork、Line Workなどを活用すると便利です。
2. 受け入れ直前(2〜4週間前)
入社が近づいたら、生活面の準備に移ります。
住居・生活環境の確認
住居の契約、家具・家電の準備、交通アクセス、近隣のスーパーや病院などを事前に確認しておきましょう。日本に在留している外国人でも、引っ越しをする必要がある場合には、住居の確保や、各種手続きが必要となってきます。
また、家具・家電の準備は義務ではありませんが、国外から招聘する場合は、入国後すぐに生活ができるよう、家具・家電なども用意をしておいてあげると、定着率の向上につながります。
生活オリエンテーションの準備
ゴミの出し方、公共交通の使い方、緊急時の対応などを説明する資料を、本人が理解できる言語で用意します。入管のホームページでも生活オリエンテーションに使える資料を公表しています。また、ごみの出し方は各自治体で異なりますので、外国人の住所のある市区町村役場で、ゴミ出しの表をもらっておきましょう。自治体によっては外国語で書いた表を作成しているところもあります。
社内研修の実施
既存社員向けに「やさしい日本語」や文化理解の研修を行うことで、受け入れ体制がスムーズになります。これと併せて、外国人がその事業所や店舗で孤立しないよう、見守る体制づくりが必要です。何も特別なことをする必要はなく、リーダーや同じぐらいの年齢の従業員に声掛けなどをお願いしたり、歓迎会を開くなどして、楽しく働いてもらえる職場環境を作っていきましょう。
3. 入社後〜初月
いよいよ支援の本番です。初月は特に丁寧な対応が求められます。
生活オリエンテーションの実施
対面またはオンラインで、生活ルールや地域情報を説明します。外国人が理解できる言語で行う必要がありますので、通訳者の同席があると安心です。
実施方法としては、対面以外にテレビ電話や DVD 等の動画視聴によるものでもかまいません。その場合は、特定技能1号外国人からのその内容について質問があった場合に、適切に応答できるようコミュニケーションがとれる体制を整備していおいてください。
生活オリエンテーションの実施
特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。
公的手続き等への同行
公的手続き等への同行も努力義務となっています。
住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出
1号特定技能外国人が、これらの届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じ、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助をするなどの必要な支援を行わなければなりません(特に、国民健康保険及び国民年金に関しては、外国人自身が手続を行う必要があることから、手続を円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましい。)。
抜粋:法務省|1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-運用要領別冊
4. 月次・定期支援(継続運用)
支援は「やって終わり」ではなく、継続的な運用が求められます。
3カ月に1回以上の相談対応・面談
仕事や生活に関する悩みを聞き、必要に応じて対応します。記録は必ず残しましょう。届出は年に1回で済むようになりましたが、面談は3カ月に1回以上行うことが必要です。
支援記録の更新と保存
支援内容は3年間保存が必要です。記録の抜け漏れがないよう、定期的にチェックしましょう。
変更・問題発生時の届出
特定技能1号の外国人に関して、変更や問題が生じた場合には、管轄の出入国在留管理局への届出が必要です。
届出が必要となる変更や問題には、以下のようなものがあります。こうした変更や問題が発生した際に行う届出は「随時届出」と呼ばれます。
・雇用条件が変わった
・退職した(雇用契約の終了)
・新たな雇用契約を結んだ
・雇用を続けることが困難な事由が生じた
・支援計画が変わった
・支援の委託先が変わった
など
届出については、下記のブログ記事で詳しく解説しています。

その他の支援
これらに加えて、日本語学習の支援や日本人との交流の機会の提供、さらには病気やけがの際の対応なども必要です。
特定技能1号で来日する外国人の多くは、単身で渡航し、日本国内に頼れる人がいない場合も少なくありません。そうした状況を踏まえ、適切な支援を行うことで、安心して長期的に働いてもらえる環境づくりが求められます。
まとめ:スケジュール管理が信頼と定着率を生む
自社支援は「準備・実施・記録」の3ステップが鍵です。スケジュールを可視化することで、社内の協力体制も整いやすくなり、外国人社員との信頼関係を築くことができます。
「支援=義務」ではなく、「支援=育成と定着への投資」と捉えることで、企業にとっても大きなメリットが生まれるはずです。
「自社支援に切り替えたいが、何から始めればよいか分からない」「分からないことが多く、詳しく教えてほしい」といったご相談がありましたら、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。
登録支援機関での実務経験を持つ女性行政書士が、親身になって丁寧にサポートいたします。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。