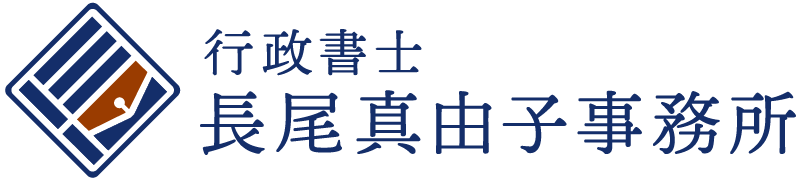特定技能1号制度を活用して外国人材を自社支援で受け入れる企業にとって、入国後の初期支援は、非常に重要であると同時に、企業の支援業務の中でも最も手間と労力を要する工程です。適切なサポートを行うことで、外国人本人の不安を軽減し、企業への信頼感を高めることができます。また、定着率の向上やトラブルの未然防止にもつながります。
この記事では、外国人が日本に入国した直後に、自社支援を試みる企業が行うべき支援内容の中でも、空港での出迎え、役所や郵便局での手続き、生活支援について、具体的かつ実務的に解説します。
空港での出迎えと初期案内
外国人が日本に到着する瞬間は、文化や言語の違いに戸惑いや不安を感じやすいタイミングです。企業が空港で出迎えることで、「受け入れられている」という安心感を与えることができます。
空港での出迎えは、単に担当者が空港まで迎えに行けば良いというものではありません。義務ではありませんが、事前に以下の準備を整えておくことで、スムーズに外国人を出迎えることができます。
- 個々の外国人との直接的な連絡手段の確保
- 到着ゲートの確認と名前入りプレートの準備(会社名やロゴがあると安心感UP)
- 滞在先までの送迎手段を事前に手配(社用車、タクシー、公共交通機関など)
- 初日のスケジュールや翌日の手続き内容等の説明準備
1.個々の外国人との直接的な連絡手段の確保
以外と見落とされがちですが、非常に重要なのが「個々の外国人との直接的な連絡手段の確保」です。今回は、海外から外国人を空港で迎えるためのポイントについて取り上げていますが、実際に海外から人材を招聘する過程では、大小さまざまなトラブルが発生する可能性があることを覚悟しておく必要があります。
外国人が日本に到着するまでは、現地で何が起きているのかを正確に把握するのが難しく、送出し機関だけでは情報が十分に届かないこともあります。そんな時こそ、個々の外国人と直接連絡が取れる環境があると、状況把握や迅速な対応に大きく役立ちます。
LINE、Facebook、Instagramなど、どのツールでも構いません。本人とスムーズに連絡が取れる手段を事前に確認・共有しておくことが、トラブル回避と信頼関係の構築につながります。
2.到着ゲートの確認と名前入りプレートの準備
到着ゲートは必ず事前に確認しておきましょう。そして、外国人の到着時刻よりも早めにゲートに到着し、会社名入りのプレートを持って待機することが重要です。これは単なる歓迎の意を示すためだけでなく、入国直後のトラブルを未然に防ぐための実務的な対応でもあります。
特定技能制度では、外国人材が入国後すぐに所在不明となった場合、企業の監理責任が問われる可能性があります。状況によっては、出入国在留管理庁からの指導や、特定技能外国人の受け入れ停止措置が科されることもあります。特に、企業側の不備や支援計画の未実施が原因と判断された場合、最大5年間の受け入れ禁止などの厳しい制裁が課されることもあるため、慎重な対応が求められます。
そのため、空港での出迎えは「逃亡防止の対策を適切に講じている」ことを社内外に示す重要な行動でもあります。企業としての信頼性を保ち、制度上の義務を果たすためにも、到着時の対応は万全に整えておきましょう。
3.滞在先までの送迎手段を事前に手配(社用車、タクシー、公共交通機関など)
送迎は社用車で行われることが多いと思います。社用車や公共交通機関を使用しての送迎は問題ありませんが、送迎のみを登録支援機関などに外部委託する場合などには注意が必要です。
以下は、出入国在留管理局のホームページに掲載されている、「様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書【記載例】」の一部を抜粋しています。
車両を利用する送迎方法について,特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を有していない場合には、道路運送法違反となる可能性が高いため,公共の交通機関を利用してください。
言うまでもありませんが、社用車で空港へ迎えに行く際には、外国人の人数や荷物の量を考慮し、車両のサイズや台数を適切に見積もる必要があります。事前に、スーツケースの個数や荷物の大きさなどを本人に確認し、共有しておくことで、当日の対応がスムーズになります。
4.初日のスケジュールや翌日の手続き内容等の説明資料準備
初日のスケジュールは、あらかじめ簡潔に説明できるよう準備しておきましょう。翌日からすぐに業務を開始してもらうケースも少なくないため、初日に市役所での住民登録や、銀行・郵便局での口座開設など、必要な手続きを済ませることが求められる場合があります。
また、スケジュール的に外国人本人が同行できない手続きについては、委任状が必要になることもあります。そのため、初日のうちにサインや印鑑をもらっておくことで、後日の手続きを円滑に進めることができます。
国籍や性格によっては、手続きに対して非常に慎重な姿勢を示す外国人もいます。そのため、サインや押印の目的や意味について、本人が納得できるように説明できる資料を準備しておくことが重要です。特に、当該外国人の母国語で作成した説明資料があると、誤解や不安を防ぎ、トラブルの予防につながります。
市区町村役場での転入届(住民登録)
転入届のポイント
日本での生活を始めるには、まず住民登録が必要です。転入届を提出することで、住民票が発行され、各種手続きに必要な基盤が整います。
転入届の手続きは、市区町村役場によって方法や必要書類、提出・提示すべき書類が異なるため、事前に管轄の市区町村役場へ問い合わせて確認することが不可欠です。
多くの自治体では、委任状を持参すれば代理人による転入届の提出が可能ですが、委任状の様式や記載内容も自治体ごとに異なります。また、申請書類や委任状をホームページからダウンロードできる自治体もあれば、窓口で直接受け取る必要がある自治体もあるため、事前の確認は必須です。
ホームページから様式をダウンロードできる場合は、社内であらかじめ記入して持参することで、窓口での手続きがスムーズに進みます。特に、外国人の受け入れ人数が多い場合は、こうした事前準備が業務効率の向上につながります。
主な必要書類
必要書類は、市区町村役場によって異なる場合がありますので、必ず事前に管轄の役場へ確認してください。ただし、全国的に共通して求められることが多い書類もありますので、以下を参考にして準備を進めると安心です。
本人提出の場合
- 転入届届出用紙(市区町村によって用紙の名称が異なります)
- 在留カード
- パスポート
- 賃貸契約書(または滞在先の証明)
代理人提出の場合
上記に加えて
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
同行のすすめ
言語の壁があるため、企業担当者が同行してサポートするのが理想です。市区町村役場によっては外国語対応が限られているため、事前に対応可能な窓口を確認しておくとスムーズです。また、同行した際には、当該外国人の母国語で書かれた各種案内書をもらっておくことをおすすめします。
注意点:
住民登録後に発行される住民票は、銀行口座開設や携帯契約などに必要となるため、必ず取得しておきましょう。
マイナンバー通知カードの取得と活用
転入届を提出すると、数日〜数週間後にマイナンバー通知カードが郵送されます。マイナンバーは税務、社会保険、銀行口座開設などに必要な個人識別番号です。
企業が伝えるべきこと
- マイナンバーの重要性と用途(給与支払、年末調整、保険加入など)
- 紛失時の再発行手続き
- 通知カードが届くまでの期間と保管方法
補足:
マイナンバーカードの取得は任意ですが、本人確認書類として非常に便利なため、希望者には申請方法を案内しておくと親切です。特に、在留資格の更新時に必要となる課税証明書や納税証明書の取得において、マイナンバーカードがあればコンビニでの発行が可能になる市区町村もあり、業務の効率化にもつながります。
銀行口座の開設(給与振込用)
給与振込のためには銀行口座の開設が必須です。外国人対応のある銀行を選定し、必要書類を整えてサポートしましょう。
おすすめ銀行
- ゆうちょ銀行(全国対応、ATMが多い)
- 三菱UFJ銀行(英語対応あり)
- 楽天銀行(オンラインで開設可能)
必要書類
- 在留カード
- 住民票
- 印鑑(銀行によっては不要)
注意点:
銀行によっては在留期間が短いと口座開設を断られる場合があるため、事前に確認が必要です。また、手続きや必要書類についても、銀行によって異なる場合があるので、事前確認をしておきましょう。
郵便局での住所登録・ゆうちょ口座開設
郵便局では、住所登録やゆうちょ銀行の口座開設が可能です。ゆうちょは全国に支店があり、ATMの数も多いため、外国人にとって使いやすい銀行です。
支援内容
- 郵便物の転送設定(旧住所がある場合)
- ゆうちょ口座の開設サポート
- ATMの使い方や通帳の管理方法の説明
同行のすすめ
郵便局は全国に多数あり、小規模な局も多く存在します。そのため、外国人対応に不慣れな郵便局も少なくありません。外国人が口座開設を希望すると、「どなたか日本人の方がご同行されますか?」と、不安そうに尋ねられることがあります。そして、日本人が同行すると伝えると、ほっと安心されるケースが多いです。
事前確認のすすめ
また、口座開設をインターネットで行わない場合は、本人が郵便局の窓口へ直接出向く必要があります。特に、端末が1台しかないような小規模な郵便局では、手続きに時間がかかることがあり、複数人を同時に対応することを避けたがる傾向があります。
そのため、郵便局で外国人の口座開設を行う際には、事前に以下の点を確認しておくことをおすすめします:
- 同日に何人まで対応可能か
- 日本人の同行が必要かどうか
- 申込書を事前にインターネットで作成していった方が良いのか
携帯電話・SIMカードの契約
携帯電話は生活に欠かせないインフラです。外国人対応のあるキャリアを紹介し、契約時の注意点を説明しましょう。
また、携帯キャリアによって契約内容や手続き方法が異なるため、事前に電話などで確認しておくことをおすすめします。近年では、外国人が自身の端末を持参するケースも増えていますが、外国製の端末にSIMカードのみを入れ替えたい場合などは、電話での確認だけでは対応可否が分からないことも多く、店舗での確認が必要になる可能性が高いです。
おすすめキャリア
- ソフトバンク(英語対応あり)
- 楽天モバイル(契約が簡単)
- 格安SIM(低価格で利用可能)
契約時の必要書類
- 在留カード
- 住民票
- 銀行口座またはクレジットカード
注意点:
契約期間や解約手数料など、日本独特のルールがあるため、事前に説明しておくとトラブルを防げます。
生活オリエンテーション
生活に関する基本的なルールや情報を伝えることで、外国人が地域社会にスムーズに馴染むことができます。
オリエンテーション内容例
- ゴミの分別方法と収集日
- 交通機関の使い方(ICカード、乗り換え案内)
- 緊急連絡先(警察、消防、病院)
- 近隣の商業施設(スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど)
- 食文化や宗教配慮(ハラール、ベジタリアン、アレルギー対応)
企業の工夫
多言語の生活ガイドを配布したり、先輩外国人社員による説明会を開催することで、より実践的な支援が可能です。
まとめ:企業の支援が外国人材の安心と定着につながる
特定技能1号で来日する外国人にとって、入国直後の支援は生活の土台を築く重要なステップです。企業が丁寧にサポートすることで、安心して働き始めることができ、長期的な雇用関係の構築にもつながります。
この記事で紹介した支援内容は、すべて実務的で再現性のあるものばかりです。ぜひ貴社の自社支援での受け入れ体制の整備にお役立てください。
「自社支援に切り替えたいが、何から始めればよいか分からない」「分からないことが多く、詳しく教えてほしい」といったご相談がありましたら、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。
登録支援機関での実務経験を持つ女性行政書士が、親身になって丁寧にサポートいたします。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。