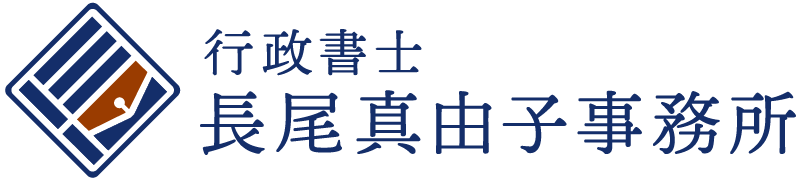義務的支援とは
特定技能1号の義務的支援とは、所属機関が外国人に対し、生活・職業面で必要な支援を継続的に提供する法定の責務です。登録支援機関に全部の義務的支援を委託している場合は、受入れ機関所属機関がその責務を果たしているとみなされます。
ということは、現在登録支援機関に全部の支援を委託している所属機関は、自社で支援をしようとする場合、以下の義務的支援を全て自社で行う必要があるということです。
義務的支援には、次の10項目があります。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
義務的支援の内容⑥~⑩
前回のブログ記事で、①~⑤の義務的支援の内容を書きましたので、今回は⑥~⑩の義務的支援の内容について書いていきます。
⑥日本語学習の機会の提供
○ 日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
① 就労・生活する地域の日本語教室や認定日本語教育機関等に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が登録日本語教員等と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること
⑦ 相談・苦情への対応
○ 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
○ また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
○ 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
⑧日本人との交流促進
○ 1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
○ また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
所属機関(受入れ機関)の都合により特定技能外国人を解雇する場合は、特定技能外国人の転職を支援しなければなりません。
○ 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
① 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
② 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④ 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
○ 上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
・ 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・ 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
○ 特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
○ 特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
○ 面談対象者(1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある者)が同意している場合は、オンライン会議システムやテレビ電話(面談担当者と面談対象者が互いに表情等を確認しながら会話が可能なシステム)等を活用した面談(以下「オンライン面談」といいます。)を実施することも可能です。
○ オンライン面談の実施のための特定技能外国人の同意については、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の「Ⅳ支援内容 9定期的な面談の実施・行政機関への通報」欄の記載及び末尾の署名欄により確認を行ってください(特定技能外国人の監督をする立場にある者については、任意の様式で同意の確認をして差し支えありません。)。
○ 既に実施中の1号特定技能外国人支援計画に基づく定期的な面談について、オンライン面談を実施する旨の支援計画変更に係る届出は不要ですが、面談対象者の同意を確認した書面については、帳簿書類として保存する必要があります。
○ オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意してください。
① 面談対象者の同意がない場合や(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合には、対面による面談を実施する必要があります。
② オンライン面談の様子を録画して一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
③ オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合には、改めて対面による面談を行う必要があります。
○ 定期的な面談の実施については、支援責任者又は支援担当者が実施する必要があるため、特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。なお、この場合であっても、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を履行補助として委託して同席させることはできます。
○ 定期的に行う面談の場においては、前記(4)の生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。
○ 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
○ 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
○ 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
○ ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談について、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
本ブログ記事の内容は、法務省発行の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領別冊」を元にしています。こちらには、義務的支援だけでなく、任意的支援も書かれていますので、特定技能外国人を自社支援する場合の参考にして下さい。
義務的支援だけでも、これだけのボリュームがあります。登録支援機関に支払う料金を節約し、自社で特定技能外国人を支援をしようとする場合には、体制を作るための時間やコストを覚悟しなければなりません。
自社支援に切り替えたいが、「何から始めて良いかわからない」、「どうすれば効率的に自社支援ができるのか」などのお悩みをお持ちの場合は、行政書士や自社支援サポートサービスを提供している会社などを活用するのも一つの方法です。
行政書士長尾真由子事務所では、登録支援機関での就業経験のある行政書士が、自社支援への移行についてのご相談も承っております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。