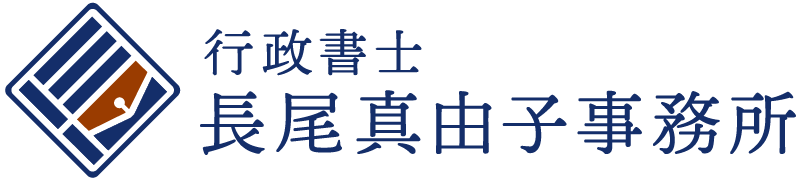外国人材の受け入れが進む中で、特定技能1号制度を活用する企業が増えています。
その中でも、「登録支援機関に委託せず、自社で支援を行う」という選択肢が注目されています。
また、実際に自社支援に踏み切った所属機関さんのお話も聞くようになりました。
この記事では、特定技能1号外国人に対する「自社支援」のメリットとデメリットを、実務の視点からわかりやすく解説します。
そもそも「自社支援」とは?
特定技能1号の外国人を雇用する企業は、法律で定められた支援項目(生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習支援など)を実施する義務があります。
義務的支援については、下記の2つのブログ記事で、詳しく解説しています。


この支援を外部の「登録支援機関」に委託することもできますが、企業自身が行う場合は「自社支援」と呼ばれます。
制度理解と体制整備が必要ですが、うまく活用すれば企業にとって大きなメリットがあります。
自社支援のメリット・デメリット
自社で支援を行うことには、コスト削減をはじめとする多くのメリットがあります。
しかし、メリットばかりではありません。最大の課題は、「外国人材への支援をすべて自社で担うのは想像以上に手間がかかる」という点ではないでしょうか。
そのために、登録支援機関という制度が設けられているのです。
支援体制を整え、必要な知識を習得し、適切に運用していくには、相応の労力と時間が求められます。これまでであれば、登録支援機関に任せていた部分について、「費用を払っているのだから、対応してほしい」と依頼することができました。
しかし、自社支援を選択した場合は、すべての責任を所属機関が直接負うことになります。外部に頼れる相手がいなくなるという点も、慎重に検討すべきポイントです。
自社支援のメリット
1.コスト削減
企業が「自社支援」へ切り替えたい最大の理由は、支援にかかるコストの削減でしょう。登録支援機関への委託費用(月額1万〜3万円/人)を抑えることで、限られた予算を人材育成や福利厚生に充てることができ、結果として優秀な人材の確保につながります。
2.柔軟な対応が可能
自社の業務内容や企業文化に即した支援が可能なため、外国人社員がよりスムーズに職場に馴染むことができます。登録支援機関にすべてを任せている企業の中には、特定技能1号労働者に対して無関心で、問題対応をすべて外部任せにしているケースも見受けられます。そのような姿勢は、外国人社員に不信感を与え、離職につながりやすくなる恐れがあります。
3.社内の理解促進
支援を通じて社員同士のコミュニケーションが深まり、外国人材への理解が進みます。これにより、職場の多文化共生が促進され、社内の雰囲気も良くなり、外国人だけでなく、日本人の定着率の向上にもつながります。
さらに、多様性を尊重する職場づくりは、企業のブランド価値や採用力の強化にも寄与します。実際に国際的な職場環境をアピールすることで、毎年、新卒採用に成功している介護施設もあります。
4.スピード感のある対応
外部との調整が不要なため、急な相談やトラブルにも迅速に対応できます。登録支援機関が必ずしも近隣にあるとは限らず、緊急時にすぐ駆けつけてもらえるとは限りません。そのため、「費用を支払っているのに何もしてくれない」と不満を抱く所属機関も少なくありません。自社支援であれば、こうした不安を軽減し、より機動的な対応が可能になります。
自社支援のデメリット・注意点
1.制度理解と運用負担
支援項目は法令で細かく定められており、実施記録の保存も必要です。
担当者には制度の理解と継続的な運用力が求められます。特に入管の制度は毎年何かしらの改訂があります。今までは登録支援機関から知らせてもらっていた情報も、自社で積極的に収集しなくてはなりません。また、分からないことがある場合は、自社で入管や役所に問い合わせる必要もあります。
2.言語対応の課題
支援は、特定技能1号外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。言語の壁がある場合、支援内容の誤解や不履行につながり、結果として在留資格や企業の信頼に影響を及ぼす可能性があります。
とはいえ、常駐の通訳者を社内に配置する必要はなく、必要に応じてスポット的に通訳・翻訳業務を外部委託することで対応することも可能です。ただし、外注のタイミングや品質管理には注意が必要であり、支援の継続性や緊急時の対応体制についても事前に検討しておくことが望まれます。
3.人的リソースの確保
支援責任者および支援担当者の選任と教育は不可欠です。両者を同一人物が兼任することも可能ですが、業務負担を軽減するためには、役割を分担し、別の担当者を配置する方が望ましいでしょう。
特に、昨今の人手不足を踏まえると、支援業務に人的リソースを割けるかどうかは慎重に検討すべき課題です。必要に応じて、社内体制の見直しや業務の再配置も視野に入れる必要があります。
4.入管対応の責任
支援が不十分と判断された場合、企業の信用や外国人材の在留資格に影響を及ぼす可能性があります。対応を誤ると、所属機関のみならず、外国人本人が法的責任を問われる事態となり、当該外国人の人生に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
さらに、入管当局から問題があると疑われた場合には、査察が入る可能性も否定できません。その際の対応はすべて所属機関が担うこととなり、業務負担やリスクの増大が想定されます。
自社支援を成功させるには
自社支援を成功させるために、押さえておきたいポイントまとめました。
1.支援計画書や記録様式をテンプレート化し、社内マニュアルを整備する
支援内容は法令で定められており、記録保存も義務です。テンプレート化することで担当者間の認識を統一し、記録漏れや対応のばらつきを防げます。社内マニュアルには、記入例・保存方法・更新頻度なども明記しておくと安心です。
2.通訳者とのスポット契約や、翻訳アプリ・オンライン通訳の活用
常時通訳者を雇用するのが難しい場合は、必要時に依頼できるスポット契約が有効です。加えて、翻訳アプリやZoom等のオンライン通訳サービスを併用することで、コストを抑えつつ多言語対応が可能になります。緊急時の連絡先リストも整備しておきましょう。
3.外部専門家(行政書士、通訳者、研修講師)との連携を視野に入れる
支援業務は法的・文化的な専門知識が求められる場面も多く、社内だけで対応しきれないこともあります。行政手続きや研修設計などは、専門家と連携することで正確性と信頼性が向上します。顧問契約やスポット相談の体制を整えておくと、トラブル時にも迅速に対応できます。
4.社内研修で「文化理解」や「やさしい日本語」の活用を促進する
外国人社員との円滑なコミュニケーションには、言語だけでなく、文化的背景への理解が欠かせません。「やさしい日本語」や非言語コミュニケーションに関する研修を通じて、現場の受け入れ体制を強化しましょう。支援担当者だけでなく、現場の上司や同僚も対象にすることで、職場全体の意識向上につながります。
また、日本語や日本文化を教えるだけでなく、特定技能1号の外国人から彼らの言語や文化を教えてもらう機会を設けることも大切です。堅苦しく考える必要はありません。「これは○○語で何と言うの?」「名前を○○語で書いてみて」など、気軽な質問から始めてみましょう。
さらに、イベントの際には、特定技能1号の外国人に母国の民族衣装を着てもらったり、料理をふるまってもらったり、写真や動画を紹介してもらうのも楽しい交流のきっかけになります。実際、ある介護施設の夏祭りでは、民族衣装に身を包んだ外国人スタッフが自国の料理を提供しており、参加者から大変好評でした。私自身も義母の家族として参加しましたが、とても楽しく、心温まるイベントでした。
まとめ
自社支援は時間と手間がかかるものの、導入することでコスト削減につながるだけでなく、社内における外国人労働者への理解と意識が高まります。
その結果、国際的な職場としての魅力を発信でき、外国人だけでなく日本人の採用にも好影響を与える「企業の顔」となります。
両者の定着率が向上し、安定した人材確保にもつながるでしょう。
「自社支援に切り替えたいが、何から始めればよいか分からない」「分からないことが多く、詳しく教えてほしい」といったご相談がありましたら、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。
登録支援機関での実務経験を持つ女性行政書士が、親身になって丁寧にサポートいたします。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。