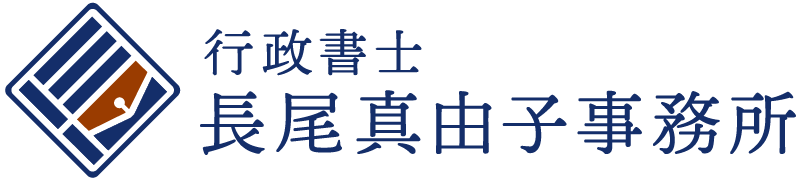はじめに
2025年4月21日、特定技能介護分野における訪問介護の受け入れがついに解禁されました。しかし、受入れ機関である訪問介護事業者には、今まで特定技能外国人の受入が可能であった介護施設よりも、多くの条件が付されることとなっています。特に、外国人が特定技能1号の介護経験者であることが求められることから、現実的に人材不足解消になるのかが懸念されるところです。
ただ、そうは言っても、現状訪問介護の人手不足は顕著ですので、今ある訪問介護の事業所を存続させるためには、外国人人材の活用を考えていかなければならないでしょう。
特定技能制度では、外国人を雇う側の事業者のことを、受入れ機関または所属機関と言います。受入れ機関の人事の担当の方は、まずは制度の概要を知り、自分たちがどのような体制を整えていけば良いのかを把握しておきましょう。
以下のブログ記事は、特定技能の概要と、全分野の受入れ機関が確認しておくべき事項をまとめた記事となります。今回の記事を読む前にお読みいただけると、より理解が深まると思います。

特定技能「介護」の受入れ機関の要件
上記ブログ記事では、全ての分野(現在16分野)の受入れ機関が守るべき条件を確認していただきました。
特定技能制度では、それぞれの分野ごとに「上乗せ基準告示」が設けられています。次に、「介護」の受入れ機関では、どのような要件が必要となるのかを見ていきましょう。特定技能「介護」分野の「上乗せ基準告示」も改正に合わせて改訂が行われています。
上乗せ基準告示第2条
特定技能「介護」分野の上乗せ基準告示第2条には、受入れ機関が遵守すべき基準が明記されています。
告示第2条
介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させない場合には、第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一 一号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務を行うものであること。
二 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する場合にあっては、実務経験等を有する一号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、一号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次に掲げる事項を遵守することとしていること。
イ 一号特定技能外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。
ロ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する際、従事し始めた時から当該一号特定技能外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。
ハ 一号特定技能外国人が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該一号特定技能外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体的な内容、当該一号特定技能外国人の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。
ニ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。
ホ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。
三 一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の介護の在留資格、5の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
四 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。
五 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
六 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
七 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
「上乗せ基準告示第2条」の要点
「上乗せ基準告示第2条」は少し読みずらい文章だったかと思いますので、要点をまとめてみました。
- 受入れ機関が介護等の業務を行っていること
- 外国人介護人材を雇用するに当たっては、実務経験1年以上の1号特定技能外国人を雇用すること
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその移行等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のために相談窓口設置等の必要な措置を講じること
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
- 1号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(外国人介護福祉士、永住者、日本人の配偶者等を含む)の総数を超えないこと
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に入会すること
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
特定技能で訪問介護が解禁されたことを受け、外国人雇用に前向きな事業様もおられることでしょう。ただ、現在のところ、実務経験1年若しくは日本語能力がN2以上と、人材確保に課題のある制度となっているため、特定技能の制度の趣旨である、人材不足の産業分野の人材不足解消になる制度なのかどうかは疑問が残るところです。
だからといって、この制度の使用をためらっている場合ではない事業者の方も多いでしょう。
次回は、訪問介護事業所である受入れ機関の遵守事項である、「上乗せ基準告示第2条」をもう少し具体的に解説したいと思います。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。