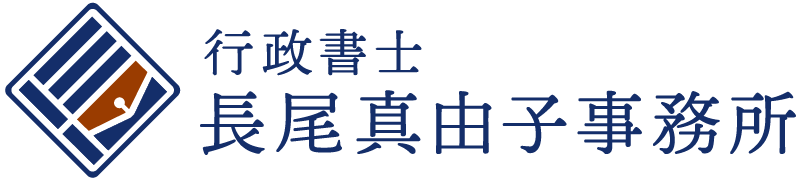はじめに
前回のブログ記事で、外国人が日本国籍を取得するのは難しいと言われている理由についてお話しました。その中で、7つの要件を書きましたが、今回はその要件をもう少し詳しく解説していきたい思います。
前回のブログ記事はこちらからご覧になれます。

外国人が日本国籍を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。この条件は、日本の「国籍法」第5条によって定められています。ただし、「国籍法」によって定められている要件は6つあるのですが、実際はもう一つ、日本語の要件も満たす必要があります。
具体的には以下の7つの要件をクリアしなければなりません。「」内は第5条の文言です。
- 居住要件ー「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
- 能力要件ー「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」
- 素行要件ー「素行が善良であること。」
- 生計要件ー「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
- 国籍要件ー「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」
- 思想要件ー「日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
- 日本語要件
7つの帰化の要件
それでは、上記の条件を一つずつ解説していきます。
1.居住要件
国籍法第5条1項1号では、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」となっています。なぜ、引き続きと書かれているのでしょうか?それは、日本に5年住んでいれば、なんでも良いというわけではないからです。当然のことながら、不法滞在で日本に5年住んでも、この要件は満たされません。
適正な中長期の在留資格ををもって、日本に住み続けたという実績が必要です。また、在留資格も期間が限定されているものは適正とは言えません。技能実習や特定技能1号などは、期間に定めがあり、その期間が終了すれば帰国することが前提となっているからです。
また、長期の海外渡航は、引き続き日本に住所を有しているとみなされませんので注意が必要です。どれぐらい日本を離れていると、要件から外れてしまうのかをお知りになりたい方は、法務局に相談されるか、帰化専門の行政書士さんに聞いて下さい。細かな要件をブログ記事に書くと、要件がどんどん厳しくなってしまいますので、ここでの記載は控えさせていただきます。
最後に、「簡易帰化」という制度についてお話ししておきます。こちらは「国籍法」6条と7条にその内容が規定されています。この法律は、次の3つの要件のうち、いずれかを満たせば5年の居住要件が緩和されるというものです。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で産まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で産まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
2号では、親子2代にわたって日本で産まれた場合、日本に住んだことがなくても居住要件を満たすことができます。
日本人の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても同様とする。
つまり、①日本人の配偶者であって、引き続き3年以上住んでいる又は、②婚姻して3年経っていて、引き続き1年以上日本に住んでいれば、5年の居住要件は緩和されます。
2.能力要件
国籍法5条1項2号では「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」と書かれています。要は、日本でも本国でも、年齢的に成人になっていることが求めらているのです。R4年4月までは日本の成人年齢は20歳でしたので、日本で成人していれば本国でも成人していることが多かったのですが、現在は18歳で成人ですので、日本で成人していても本国で成人していないかもしれません。ご自分の本国の成人年齢も大使館に問い合わせてチェックをしておきましょう。
また、成年被後見人や被保佐人などの制限行為能力者は、意思を示すことのできる能力が無い、と判断され帰化をすることはできません。
3.素行要件
国籍法5条1項3号では「素行が善良であること。」と書かれていますが、素行が善良とはどういうことなのでしょうか?
ここでいう素行とは、「法律違反が無かったかどうか」を意味しています。法律違反とは、殺人や窃盗などの重い犯罪だけでなく、軽い交通違反や不倫も含まれます。詳しい内容については、法務局に相談されるか、帰化専門の行政書士さんに聞いてみて下さい。
また、納税や社会保険の支払いがきちんとされているかも問われます。特に納税については、法務局から渡される必要書類一覧表では、相続税、贈与税、固定資産税、自動車税などの納税を証明する書類は要求されません。しかし、後で未納や滞納が発覚すると不許可になりますので、払っていない税金がある場合は、正直に法務局に伝え、支払いを済ませておきましょう。
4.生計要件
国籍法5条1項4号では、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」と書かれています。
資産は預金や不動産、株などです。技能とは、会社勤めでも、自分で会社を経営しているのでもかまいません。家族がいるのなら、家族の誰かの資産や収入で、家族全員が暮らしていけるのかが問われますが、収入や預金の額に決まりはありません。
収入や預金が少なくても、その金額内で生活ができていれば良いのです。逆に、収入が多くても、派手な生活をしていて、生活費のために借金をしているような状態では不許可となってしまいます。
日本の帰化では、それほどお金持ちでなくても許可されます。自分の収入内で慎ましく生活し、更に貯金などもできていれば、審査官の心証は良くなります。
5.国籍要件
国籍法5条1項5号では、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」とされています。
日本は重国籍を認めない国ですので、帰化をすると元の国籍を失わなければなりません。その際に注意したいのは、元の国籍の国が重国籍を認めている国かどうかです。重国籍を認めていない国の場合は、日本に帰化したと同時に、何もしなくても元の国籍を失います。
しかし、重国籍を認めている国では、帰化の前に元の国の国籍を抜けておく必要があります。ここで、ひとつ疑問がでてきますよね。帰化前に元の国の国籍を抜けて、万が一不許可になってしまったらどうするの?と。
その点、日本の法務局は親切で、重国籍を認めている国の申請者には、正式の帰化許可の前に内定を出して、元の国の国籍を抜けるよう通知してくれます。
また、、兵役を課している国も要注意です。兵役義務を果たしていないと、国籍を離脱できなと法律で定められている場合、国籍を失えず、帰化できないことになります。
6.思想要件
国籍法5条1項6号では、「日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」と書かれています。
なかなか物騒な項目ですね。上記の政府を暴力で破壊することを企てる若しくは主張する政党や団体とは、具体的にどのような団体でしょうか?
分かりやすいところで言うと、テロリストや暴力団、反社会的組織になるでしょうか。また、事件を起こした宗教団体などに加入している場合も不許可になります。ご自分が加入している場合はもちろんのこと、ご家族が加入している場合も不許可になる可能性がありますので注意が必要です。かといって、嘘の申告は絶対にやめましょう。
7.日本語要件
これは、国籍法には書かれていない要件になります。一般的に、小学校3年レベル、日本語能力試験のN3レベルの日本語能力が必要です。会話ができても、読み書きができなければ不許可となってしまいます。面接時に日本語のテストが課される場合があります。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、帰化のそれぞれの要件について、少し詳しくお話をさせて頂きました。
最後に国籍法8条で、「居住要件」、「能力要件」、「生計要件」の緩和につて書かれていますので、そちらを紹介しておきたいと思います。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
- 日本で産まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。